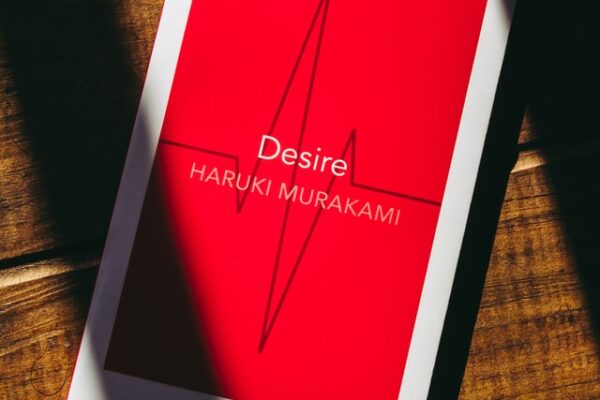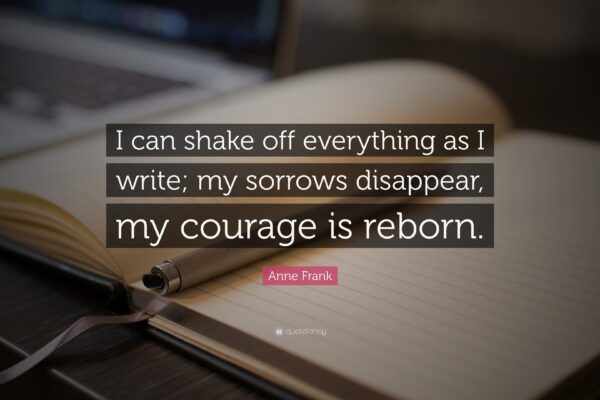言葉の「重要性」と「限界」
あなたの考えや気持ちは、言葉にしなければ人に伝わることはありません。家庭、仕事場、学校など、私たちの身の回りのあらゆる場面で言語化が必要とされています。「つうかあの仲」といえども万事が伝わるわけではないのです。また、ダイバーシティと言う言葉が示す多種多様な考え方や価値観が生まれ共存する社会では、自分の考え方・価値観を言葉にし他者に伝えるという行為は以前にも増して重要になっています。
一方で言葉の限界を理解する必要があります。メラビアンの法則によれば、”人への印象・影響”という視点では、言語情報は全体の7%しかなく、残り93%は視覚・聴覚情報によるものとなっています。つまり、見た目、声、態度などのほうが、人へ与える印象という意味では大きい影響力を持っています。「目は口ほどに物を言う」言葉がありますが、メラビアンの法則に従えば「目は口以上に物を言う」となるでしょう。
また、言葉は「目が粗いコミュニケーションツール」であることを認識しなければなりません。頭の中で認知したことを他者へ伝えるためのツールとして、人類の長い歴史の中で培われてきたものではありますが、その認知を100%言葉にするというのは大変難しいのです。自分の発した言葉が相手にうまく伝わらず「そういう意味ではない・・・」と落胆した経験を誰しも一度はあるではないでしょうか。このことについては、著作家の山口周さんの記事を引用します。
私たちが日常的に用いている「言語」はとても目の粗いコミュニケーションツールです。したがって、私たちは、自分の知っていることを100%言語化して他者に伝えることが原理的にできません。
つまり「言葉」によるコミュニケーションでは、常に「大事な何か」がダラダラとこぼれ落ちている可能性がある、ということです。
20世紀に活躍したハンガリー出身の物理学者・社会学者であるマイケル・ポランニーは「我々は、自分が語れること以上にずっと多くのことを知っている」と言い表しています。今日では、この「語れること以上の知識」を私たちは「暗黙知」という概念で日常的に用いていますが、言葉によるコミュニケーションでは常に、この「こぼれ落ち」が発生していることを忘れてはなりません。
言語化能力を高めるメリット(年収と幸福度)

言葉は、視覚情報や聴覚情報からの影響を受けやすく、また、相手側の前提知識や状態に応じても解釈(受け取られ方)が変わるため扱いが難しいものではあります。しかし、現時点で(テレパシーを習得するまでは)「言葉」が最善のコミュニケーションツールはであることは変わりません。
後に触れますが、言語化能力を構成する一つに「語彙力(ごいりょく)」があります。語彙力と収入・幸福度には関係があるというデータが出ていますので、紹介します。
ベネッセホールディングスが2016年に実施した調査では、語彙力がある人ほど、「世帯年収」および「主観的幸福度(自分は現在どのくらい幸福だと思うか)」が高い傾向があるとの結果となりました。私見ではありますが、この理由は、資料の作成・発表・プレゼン、人間関係の構築、そして自己表現などが、収入や幸福度の向上につながる多くの場面で語彙力が活かされるからではないでしょうか。
| 世帯年収1200万円以上 | 知っている語彙の割合80.3% |
| 世帯年収800万円〜1200万円 | 知っている語彙の割合72.2% |
| 世帯年収400万円〜800万円未満 | 知っている語彙の割合68.1% |
| 世帯年収400未満 | 知っている語彙の割合65.9% |
言語化の3つのプロセス(伝えるために必要な力)
ここでは、言語化のプロセスと、伝えるために必要な力を整理します。

スターディーハッカーの記事に言語化のプロセスがいくつか紹介されていますが、他者に考えや思いを伝えることを目的とする場合、私は言語化に必要なプロセスを以下のように考えます。
- <物事を認識する>
五感または気づきを介して物事を認識する。 - <整理・理解する(論理的思考力)>
因果関係、前後関係の整理や、具体化、抽象化により情報の繋がりや本質を整理・理解する。 - <言葉を組み立てる。(語彙力、構成力)>
場面、手法(口頭、記述)、相手(前提知識や状態)に応じて言葉を選択し、言葉(文)の構成を組み立てる。
「伝わらない!」という事象を、このプロセスにそって考えたとき、2また3に不足があるのでないでしょうか。頭の中にあることを話しだしたは良いが、「情報が整理されていなかった」や、「伝えるための言葉がうまく組み立てられていなかった」などの経験をしたことがある方は多いかと思います。
この、整理・理解・言葉の組み立てに必要な力が「論理的思考力」、「語彙力」、「構成力」なります。
論理的思考力・語彙力・構成力の鍛え方

「論理的思考力」、「語彙力」、「構成力」 それぞれの鍛え方について紹介します。しかし、初めに理解しなければなりません。これらは一朝一夕で身につくものではないのです。
<論理的思考力を鍛える>
論理的思考力のある人の話には、一つの特徴があります。話している内容に「原因と結果」、「根拠と結論」、「目的と手段」など、情報同士がつながりを持って存在します。物事の繋がりを見つけ論理的に考えるスキルを身につける方法として、まずは自分の決断に対し「なぜ、どうして 」と問いかけを行い、直観ではない、理由を導き出すトレーニングが有効と次の記事に紹介されています。
<語彙力 を鍛える>
前述のベネッセコーポレーションの調査結果より、語彙力が高い人の特徴を2つ見つけることが出来ます。
- 活字(本, 新聞, 雑誌)を読む時間が多い
- 自分より年上の人(語彙が豊富な人)と話す機会が多い
絶対的な量も必要ですが、どちらの場合も私は「幅(レンジ)」が重要であると考えます。現在自分が気軽に読める本や、気軽に話せる相手ではなく、新たなジャンル、難易度、価値観に触れくことが語彙力を高める秘訣だと考えます。ネットニュースを見ている方は、新聞(または新聞社の記事)を。地方新聞を読んでいる方は、経済新聞を。小説を読んでいる方はビジネス書や自己啓発本を。同業種の友人が多い場合は、異業種の方と。というようにです。
<構成力 を鍛える>
構成力が試される場、それはプレゼンテーションではないでしょうか。限られた時間の中で複数の人に向かって物事を伝える際、聞き手にとって理解のしやすい構成が求められます。このプレゼンテーションの構成を考えるための有名な手法を紹介します。日常の会話の中でも活用できる手法ですのでぜひお試しください。
- ホールパート法(話下手でもできる! 「ホールパート法」でプレゼンや報告を乗り切ろう)
話し始めの最初の部分で、これから話す分量や数を示す方法です。聞き手側に「いつまで話が続くんだろう」などの不安やストレスを与えないためにも必要な手法です。 - PREP法/SDS法(PREP法・SDS法とは?例文でわかる「意図が伝わる」構成)
PREP法(結論→理由→例→結論)と、SDS法とは(要点→詳細→要点)は文章の構成法で、相手へ物事を伝える際の構成として推奨されるものです。
アウトプットの重要性(言語化能力の高め方)
前に紹介した 論理的思考力 、 語彙力 、 構成力 の組み合わせが言語化能力となりますが、それらを総合的に身に着けるために<絶対>に必要なことが「アウトプット」です。外国語習得の場などでは「スピークアウト」とも言います。言葉の習得には、自分に向かって、または他者に向かって言葉を発信し、失敗や成功から習熟度を上げていくという方法が必要となるのです。
その一つの場として「徒然日記」をご利用いただければ幸いです。
では、「徒然日記」で引き続き素敵な日記ライフをお楽しみください!